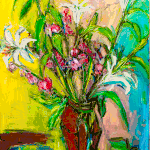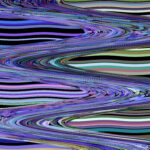「夢」
これが沢庵和尚の辞世の言葉でした。
「墓は、立ててはならぬ。」
そういって、この世を去りました。
弟子は取らず、後継者はいません。一代で終わらせました。
沢庵和尚は、江戸時代のお坊さんです。
幕府に反抗して流罪。
この権力に対しての態度は、まさに射手座の感じがしますね。
また、野心もあるというところです。
世渡り上手でもあるでしょう、忖度とは縁が遠いですが
戦略として選ぶと平気でしてしまうのが凄いところです。
木星の支配下にある射手座はとにかく実践時哲学を追求するクレバーさがあるのです。
さて、沢庵は、まさにマルチタレント。
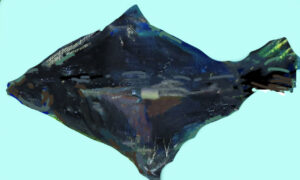
まず、習字が上手、画も、詩文も茶道も親しみ、そのレベルの高さは現代でも評価されています。
戦乱の世の中でしぶとく生き残り、関ケ原の戦いの後、32歳で大悟しました。
そのあと、大出世しましたが。37歳で重要な役職に就くものの、わずか三日でやめてしまいます。
そして、隠遁生活に入りました。
実に、もったいなく思えますが、きっと嫌だったのでしょう。
厭なことは我慢できない性格は、射手座です。
57歳の時、事件に巻き込まれて流罪となる。
60歳の許される。
なぜか家光に気に入られる。
家光もただならぬものを感じたのでしょう。
幕府に認められ、禅を説くようになりました。
何度も、「国師」の称号を断り続け、ただの一僧を貫きました。
かつての事件の後始末をきちんとして、関係者を名誉回復、全員救済しました。
多くの、帰依者や友達に囲まれていました。
柳生十兵衛とも。
これは、家光に取り入ったとも考えられますが、「そんな堅いこと言うなよ」というように、
実利を見つめることもできる、融通無碍さが射手座なのです。

時々、ふらっといなくなるので、お寺の門のところに、「沢庵番」なるものを配置していたそうです。
最後に、つけものの「たくあん」は家光の命名。
沢庵和尚が上方から持ってきたものを、家光が非常に気に入り名付けました。
和尚は、家光をさんざん待たせ腹を空かせてから、ご飯とたくわん二きれを出しました。
家光は一気に食べました。
沢庵和尚はこう言いました。
[3食なに不自由もなく食べれる人にごちそうを出すには、こういう工夫がいるのだ。] [どうだ、おいしいだろう。]
[美味しいものを食べたかったら、腹を空かせればよいのだ。]
[( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、これでいいのだ!(これは、創作)]
さて、江戸初期の自由人沢庵和尚の生き方はどうだったでしょう。
時々一休さんと間違えている人がいますが、
一休さんはみずがめ座、あの宇宙人的な感覚はみずがめ座にありがちですね。